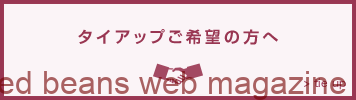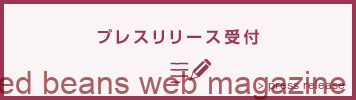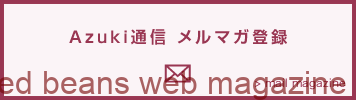おはぎ(ぼたもち)は日本の仏事「お彼岸」に、おやつに、よく食べる小豆菓子です。
蒸かしたり、炊いたりしたもち米を荒くつぶして丸め、まわりを餡で包みます。
ぼたもちには(現代ではほとんどつかわれていませんけれども)季節によって呼び名が変わります。
春は、牡丹が花咲く季節であり、形がにているとのことから、ぼたもちとされます。
秋は、萩の花が咲く季節であり、萩の花が咲き乱れている様子からおはぎとされます。
夏は「夜船」
秋は「北窓」
こちらは言葉遊びで、通常の餅と違ってもち米を 「ぺったんぺったん」とつくことがなく、
すり鉢で荒くつぶすだけなので、隣の人も餅をついたことに気づかず、
「つきしらず」であるとのことから、
夜だと暗くて 船が着いたかどうか分からないので着き知らずの船とかけて
夏は「夜船」とし、
北の窓では月が見えないので、月知らずとかけて「北窓」と呼びます。
一説には、菓子屋が彼岸におはぎをお供えしてもらうために美しい花の名前にした
ともいわれています。
また、地方によっては、
一、二口で食べられる大きさのものをおはぎ、大きなものをぼたもち、
もち米を主で作られたのものがぼたもちで、うるち米で作られたものがおはぎである
小豆餡でくるんだものが「ぼたもち」、きな粉を用いたものが「おはぎ」である
『物類称呼』(1775年)では「おはぎ」は宮中などで使われた、女房言葉であるとされます。
餅米が完全についた状態の物は「ぼたもち」、荒くついたものは「おはぎ」とされます。
物騒な呼び名ですが、完全にもち米がつかれたものを「皆殺し」
粒が残っているものを「半殺し」と呼びます。
小豆の赤色は邪気を払うという言われてました。
お彼岸(春と秋の仏事)は、赤飯のようなもち米と小豆を炊いたものを供えられていましたが、
砂糖が普及するようになるにつれ、次第に小豆餡を使ったおはぎが供えられるようになりました。
主な参考文献「あんこの本」姜尚美
「日本のたしなみ帖 和菓子」手のひらに甘美な季節
wikipedia 「ぼたもち」の項参照